コロナ禍を経て、エンジニアのリモートワークは「特別な働き方」から「標準的な選択肢」へと変化しました。私自身、完全リモートの環境で3年間働いてきた経験から、リモートワーク可の求人を見つけるための実践的な方法をお伝えします。
この記事では、単なる求人サイトの紹介ではなく、実際にリモートワークが成立する求人の見極め方、面接での確認ポイント、そしてリモートワークに適したエンジニアのキャリア戦略まで、実体験に基づいて解説していきます。
💻 レバテックキャリアで無料相談する
✅ ITエンジニア専門・業界特化型エージェント
✅ 年収アップ率77%(公式実績)
✅ 技術理解のあるアドバイザーが徹底サポート
※登録後、キャリアアドバイザーより面談日程のご連絡があります
リモートワーク求人の現状と実態
2025年現在、エンジニア求人におけるリモートワークの扱いは多様化しています。まずは現状を正しく理解することが、効率的な求人探しの第一歩です。
リモートワークの3つのパターン
エンジニア求人におけるリモートワークは、大きく3つのパターンに分類されます。それぞれの特徴と、見極めるポイントを押さえておきましょう。
完全リモート型は、オフィス出社が原則不要で、居住地の制限もないケースです。スタートアップやWeb系企業に多く、私が現在働いているのもこのタイプです。メリットは通勤時間ゼロと居住地の自由ですが、コミュニケーション能力と自己管理能力が強く求められます。
ハイブリッド型は、週2〜3日出社、残りはリモートというスタイルです。大手企業やSIerで増えているパターンで、チームビルディングとリモートのバランスを取っています。完全リモートほどの自由度はありませんが、対面でのコミュニケーションも取れるため、未経験者にとっては学びやすい環境といえます。
条件付きリモート型は、入社後一定期間経過後や、特定のプロジェクトでのみリモートが許可されるケースです。求人票には「リモート可」と書かれていても、実際にはほとんど出社が必要なこともあります。このタイプを見極めることが、転職後のミスマッチを防ぐカギになります。
業界・職種別のリモートワーク普及率
私が転職活動中に調査した結果、業界や職種によってリモートワークの普及率には大きな差があります。
Web系・SaaS企業では、バックエンドエンジニア、フロントエンドエンジニア、インフラエンジニアのいずれも8割以上がリモート対応しています。特にスタートアップでは完全リモートが標準になっており、逆に「出社必須」の求人の方が少数派です。
SIer・受託開発企業は、ハイブリッド型が主流です。顧客との打ち合わせや納品時には出社が必要ですが、開発フェーズはリモート可という企業が増えています。ただし、古い企業文化が残る会社では、依然として出社が原則のケースもあります。
社内SEは企業によって大きく異なります。情報システム部門が経営層に近い企業ではリモートが進んでいますが、現場のサポート業務が中心の場合は出社が必要なことが多いです。求人票だけでは判断しにくいため、面接での確認が必須です。
ゲーム業界は、開発職は比較的リモート対応が進んでいますが、企画職やデザイナーとの密な連携が必要な場合は、ハイブリッド型が一般的です。大手パブリッシャーよりも、インディーゲームスタジオの方がリモート率が高い傾向にあります。
求人票の「リモート可」に隠された真実
転職活動を通じて気づいたのは、求人票に「リモート可」と書かれていても、その実態は千差万別だということです。
ある企業の面接で、「リモート可」の求人に応募したにもかかわらず、「基本は出社で、月1〜2回リモートも可能」という説明を受けたことがあります。また別の企業では、「入社後半年間は出社必須、その後リモート相談可」というケースもありました。
重要なのは、求人票の表記を鵜呑みにせず、具体的な頻度や条件を確認することです。後ほど詳しく解説しますが、面接では必ず「週何日リモートワークができるのか」「リモートワークの承認プロセスはどうなっているのか」を確認する必要があります。
効率的なリモート求人の探し方
リモートワーク可の求人を効率的に見つけるには、適切なツールと戦略が必要です。私が実際に使った方法を、優先度の高い順に紹介します。
転職エージェントを活用したリモート求人の探し方
転職エージェントは、リモート求人を探す上で最も効率的な手段です。ただし、エージェントによって得意分野が異なるため、適切に選ぶ必要があります。
ワークポートは、IT・Web業界に特化しており、リモート求人の取り扱いが豊富です。私が利用した際、担当者が「週何日リモート希望か」「完全リモートか、ハイブリッドか」を細かくヒアリングしてくれ、条件に合った求人を紹介してくれました。特に20代〜30代のエンジニアで、スピード感のある転職を希望する方に向いています。
レバテックキャリアは、経験者向けのハイクラス求人に強く、完全リモートで年収600万円以上の求人を多く扱っています。キャリアアドバイザーがエンジニア出身のため、技術的な話が通じやすく、「この技術スタックならリモート向き」といった専門的なアドバイスももらえます。実務経験2年以上ある方におすすめです。
マイナビIT AGENTは、大手企業のハイブリッド型リモート求人が充実しています。安定志向の方や、福利厚生を重視する方に適しており、「週2〜3日出社、残りリモート」という働き方を希望する場合は、最初に登録すべきエージェントです。
複数のエージェントを併用する際のポイントは、それぞれに「リモートワークが最優先条件」と明確に伝えることです。私は最初、遠慮して「リモートだと嬉しいです」程度の伝え方をしていましたが、それでは優先度が低いと判断されてしまいます。「リモートワーク不可の求人は紹介不要」とはっきり伝えることで、ミスマッチが大幅に減りました。
転職サイトでの効率的な検索方法
転職サイトを使う場合は、検索条件の設定が重要です。単に「リモートワーク」で検索するだけでは、望む求人にたどり着けません。
Greenの活用法では、「リモート勤務OK」の条件でフィルタリングした後、企業の「働き方」セクションを必ずチェックします。ここには実際のリモート頻度や、社員の声が掲載されていることが多く、求人票よりも実態に近い情報が得られます。また、Greenは企業側からのスカウトも活発なので、プロフィールに「フルリモート希望」と明記しておくと、条件に合った企業からアプローチがあります。
Wantedlyの特徴は、企業文化や働き方が詳しく紹介されている点です。特にスタートアップの完全リモート求人を探す場合は有効です。「話を聞いてみたい」で気軽にコンタクトが取れるため、まずはカジュアル面談でリモート環境について詳しく聞くという使い方ができます。私はここで、リモートワークの文化が根付いている企業を複数見つけました。
検索キーワードの工夫も効果的です。「リモート」だけでなく、「フルリモート」「完全リモート」「在宅勤務」「テレワーク」など、複数のキーワードで検索すると、見落としていた求人が見つかることがあります。また、「地方在住可」「居住地不問」といったキーワードも、完全リモートの求人を見つける手がかりになります。
ダイレクトリクルーティングサービスの活用
企業から直接スカウトが届くダイレクトリクルーティングサービスは、リモート求人との出会いを広げる有効な手段です。
ビズリーチは、ハイクラス層向けのプラットフォームで、年収600万円以上の完全リモート求人からのスカウトが多く届きます。職務経歴書に「リモートワーク環境での開発経験」を具体的に記載しておくと、リモート前提の企業からのオファーが増えます。有料プランもありますが、無料プランでも十分に活用できました。
Findyは、エンジニア専門のスカウトサービスで、GitHubやQiitaのアカウントと連携できます。技術力を客観的に評価してもらえるため、実力重視のリモート企業からのスカウトが届きやすいです。私の場合、Qiitaの記事をきっかけに、完全リモートのスタートアップから声がかかりました。
LAPRASも同様に、エンジニアの技術活動を可視化してくれるサービスです。GitHubのコントリビューションやOSS活動が評価されるため、リモート環境で自走できるエンジニアを求める企業からのオファーが多い印象です。
これらのサービスを使う際のポイントは、プロフィールに「リモートワーク環境での業務経験」や「自己管理能力」をアピールすることです。単に「リモート希望」と書くだけでなく、リモートで成果を出せる根拠を示すことが重要です。
SNSとコミュニティでの情報収集
意外と見落とされがちですが、TwitterやLinkedInなどのSNS、そしてエンジニアコミュニティは、リモート求人の宝庫です。
Twitterでの探し方では、「#エンジニア採用」「#リモートワーク」「#フルリモート採用」などのハッシュタグをフォローします。企業の採用担当者や現役エンジニアが、求人情報や社内の雰囲気を発信していることが多く、求人サイトには載っていない情報が得られます。私は実際に、Twitterで見つけた企業に応募し、内定を得た経験があります。
LinkedInの活用では、英語が得意なら海外企業のフルリモート求人も視野に入ります。日本在住のまま、海外企業で働くという選択肢もあり、時差の関係で深夜勤務になることもありますが、年収が大幅にアップするケースもあります。
エンジニアコミュニティでは、勉強会やオンラインイベントで知り合った人から、「うちの会社でリモートエンジニア募集してる」という情報を得ることがあります。リファラル採用の場合、通常の選考よりも話が早く進むことが多く、リモート環境についても率直に聞きやすいメリットがあります。
リモートワーク求人の見極め方
求人を見つけただけでは不十分です。その企業が本当にリモートワークが成立する環境なのかを見極める必要があります。
求人票でチェックすべき5つのポイント
求人票を見る際、私が必ずチェックしている項目を紹介します。
1. リモートワークの具体的な頻度と条件
「リモートワーク可」という記載だけでなく、「週何日」「完全リモート可」「入社後すぐに可能か」といった具体的な情報があるかを確認します。これらの情報が明記されている企業は、リモートワークを制度としてしっかり運用している証拠です。
2. 使用ツールとコミュニケーション環境
SlackやZoom、Notionなどのツールが明記されているかも重要です。これらのツールを積極的に使っている企業は、リモートワークのための環境が整っています。逆に、ツールについて何も触れられていない場合は、リモート環境が未整備の可能性があります。
3. 在宅勤務手当やリモート支援制度
在宅勤務手当、通信費補助、PC・モニターの貸与など、リモートワークを支援する福利厚生が充実しているかを確認します。これらの制度がある企業は、リモートワークを一時的な対応ではなく、長期的な働き方として捉えている傾向があります。
4. チームの構成と働き方
「分散型チーム」「フルリモートチーム」といった記載があれば、チーム全体がリモート前提で動いている可能性が高いです。一方、「本社勤務のメンバーが多数」という記載がある場合は、リモートワーカーが少数派で、情報伝達に苦労する可能性があります。
5. 採用プロセス
最終面接までオンライン完結できるかも、一つの指標です。完全リモート企業の場合、採用プロセス自体もオンライン完結が当たり前です。逆に、「最終面接は必ず来社」という企業は、リモートよりも対面を重視する文化がある可能性があります。
企業の本気度を測る質問リスト
面接では、以下の質問をすることで、企業のリモートワークに対する本気度が見えてきます。
リモートワークの実施率について 「現在、チームの何割がリモートワークをしていますか?」という質問は必須です。「制度上は可能だが、実際にはほとんどの人が出社している」というケースは意外と多いです。私が内定を辞退した企業の一つは、「リモート可」と書かれていたものの、実際には5%程度しかリモートワーカーがいませんでした。
コミュニケーションツールと運用ルール 「リモートワーク時のコミュニケーションツールは何を使っていますか?」「レスポンスの期待値はどれくらいですか?」と聞きます。SlackやTeamsでの非同期コミュニケーションが基本なのか、Zoomでの常時接続が求められるのかで、働きやすさが大きく変わります。
評価制度とキャリアパス 「リモートワーカーと出社者で、評価や昇進に差はありますか?」という質問も重要です。残念ながら、リモートワーカーが評価されにくい企業も存在します。成果主義を謳っていても、「顔を合わせる機会が多い方が有利」という暗黙のルールがある企業もあります。
オンボーディングプロセス 「入社後のオンボーディングはどのように行われますか?」と確認します。リモート環境でのオンボーディングがしっかり確立されていれば、リモートワークを制度として運用していることの証明になります。
セキュリティとインフラ 「PCやモニターは支給されますか?」「VPN環境は整っていますか?」といった技術的な質問も欠かせません。これらが整備されていない場合、セキュリティリスクだけでなく、作業効率の低下にもつながります。
面接で確認すべきリモート環境の実態
面接では、遠慮せずに踏み込んだ質問をすることが重要です。私が実際に確認した内容を紹介します。
1次面接での確認事項 人事や採用担当者との面接では、制度面の確認を中心に行います。「リモートワークの頻度」「在宅勤務手当」「出社が必要になるケース」などを具体的に聞きます。また、「リモートワークの実施にあたって、承認プロセスはありますか?」という質問で、実際の運用の柔軟性を測ることができます。
2次面接以降での確認事項 現場のマネージャーや一緒に働くメンバーとの面接では、より実務的な内容を聞きます。「普段のコミュニケーションはどのように取っていますか?」「リモートワークで困ったことはありますか?」といった、現場の生の声を引き出すことが重要です。
私が内定を承諾した企業では、2次面接で「リモートワークの課題とその解決策」について、率直に話してくれました。課題を隠さずに話してくれる姿勢に、リモートワークを真剣に取り組んでいる姿勢を感じました。
面接官への逆質問 「あなた自身はどれくらいの頻度でリモートワークをしていますか?」と面接官に直接聞くのも効果的です。面接官がリモートワークをしていない場合、その企業ではリモートワークがマイノリティである可能性があります。
要注意な「名ばかりリモート」企業の特徴
転職活動中、いくつかの「名ばかりリモート」企業に遭遇しました。そうした企業に共通する特徴を紹介します。
求人票と面接での説明が異なる 求人票には「リモート可」と書かれているのに、面接で「基本は出社」と説明される企業は要注意です。こうした企業は、求人票でリモートという言葉を集客のために使っているだけで、実際にはリモート文化が根付いていません。
「様子を見て」「慣れたら」という曖昧な表現 「まずは出社して、慣れたらリモートも相談できます」という説明は、実質的に出社が前提である可能性が高いです。「慣れたら」の基準が曖昧で、結局ずっと出社を求められるケースもあります。
リモートワークの承認プロセスが煩雑 毎回上司に申請が必要、前日までに届出が必要、理由の説明が必要、といった煩雑なプロセスがある企業は、リモートワークを推奨していません。リモートが標準化されている企業では、承認プロセス自体が不要か、非常に簡易化されています。
現場社員がほとんど出社している 面接がオンラインで行われたとしても、「現在、オフィスには何人いますか?」と聞いてみると実態が見えます。ほとんどの社員が出社している場合、リモートワークは制度上可能でも、実質的には出社が当たり前の文化です。
リモートワークに適したエンジニアの職種とスキル
すべてのエンジニア職がリモートワークに適しているわけではありません。職種によって、リモートの実現可能性が異なります。
フルリモートが実現しやすい職種
バックエンドエンジニアは、最もリモートワークが成立しやすい職種です。コードを書くことが中心で、非同期のコミュニケーションでも業務が進めやすいからです。私自身、バックエンドエンジニアとして完全リモートで働いていますが、出社の必要性を感じたことはほとんどありません。
フロントエンドエンジニアも、リモートワークに適しています。デザイナーとの連携が必要な場面もありますが、Figmaなどのツールを使えば、オンラインで十分にコラボレーションできます。私の周りでも、フロントエンドエンジニアでフルリモートの人は多いです。
インフラエンジニア・SREは、クラウドベースのインフラが主流になったことで、リモート化が進みました。オンコール対応も自宅から可能で、むしろ通勤時間を気にせず柔軟に対応できるメリットがあります。
データエンジニア・データサイエンティストも、リモートワークが実現しやすい職種です。分析作業は個人作業が中心で、結果をレポートにまとめて共有するスタイルなので、オフィスにいる必要性が低いです。
ハイブリッド型が多い職種
プロジェクトマネージャー・テックリードは、チームマネジメントが主な業務のため、ハイブリッド型が多いです。特に、チームメンバーが出社している場合は、自分も出社した方がコミュニケーションが円滑になります。ただし、チーム全体がリモート前提で動いている場合は、完全リモートも可能です。
プロダクトマネージャーは、ビジネスサイドや経営層とのコミュニケーションが多いため、完全リモートは難しいケースがあります。特に、ステークホルダーが出社している場合は、週に数日の出社が求められることが一般的です。
QAエンジニア・テストエンジニアは、テストの自動化が進んでいる企業ではリモート可能ですが、手動テストが中心の場合は、実機を使うために出社が必要なこともあります。
リモートワークに必要なスキルセット
リモートワークを成功させるには、技術力以外のスキルも重要です。
コミュニケーション能力 対面と違い、リモートでは意識的にコミュニケーションを取る必要があります。Slackでの報連相、ドキュメント化、定期的な進捗共有など、能動的に情報発信できることが求められます。私自身、リモートワークを始めた当初は、コミュニケーション不足で誤解を招いたこともありました。
自己管理能力 リモートワークでは、誰も見ていないからこそ、自分でスケジュール管理や健康管理をする必要があります。私は、ポモドーロテクニックを使ったり、毎朝のルーティンを決めたりすることで、生産性を維持しています。
文書化スキル 口頭で済ませられないリモート環境では、ドキュメント化が非常に重要です。技術仕様書、議事録、ナレッジベースなど、後から見返せる形で情報を残すスキルが求められます。私は、Notionを使って、日々の作業ログや学びを記録しています。
非同期コミュニケーション リモートでは、同期的なコミュニケーション(会議や通話)を減らし、非同期的なコミュニケーション(テキストチャット、ドキュメント共有)を増やすことが効率化につながります。「今すぐ確認したい」という衝動を抑え、相手の時間を尊重するマインドセットが必要です。
トラブルシューティング能力 リモート環境では、ネットワーク障害や開発環境のトラブルを自分で解決する必要があります。社内SEに頼れないため、基本的なITトラブルシューティングのスキルがあると、業務が止まるリスクを減らせます。
リモートワーク転職を成功させる5つの戦略
リモートワーク可の求人に転職するには、通常の転職とは異なる戦略が必要です。私が実践して効果があった方法を紹介します。
戦略1: リモートワークの実績を作る
現在の職場でリモートワークの経験がない場合でも、実績を作る方法はあります。
副業やOSS活動 GitHubでのOSS活動や、クラウドソーシングでの副業は、リモート環境での業務実績になります。私は、転職活動前に半年間、週末に副業でリモート案件をこなし、その経験を職務経歴書に書きました。面接では、「リモートで成果を出した具体例」として評価されました。
社内でのリモートワーク実績 現在の職場で、週1回でもリモートワークができる制度があれば、積極的に活用します。「リモート環境下でもプロジェクトを完遂した」という実績は、転職の際に大きな武器になります。
個人開発プロジェクト 自分でWebサービスやアプリを開発し、公開するのも一つの方法です。これは、リモート環境での自己管理能力や技術力を示す証拠になります。私は、個人で開発したWebアプリをポートフォリオに加え、面接で「このアプリは完全にリモート環境で開発しました」とアピールしました。
戦略2: リモート特化型の求人に絞る
「リモート可」ではなく、「完全リモート」「フルリモート」と明記されている求人に絞ることで、ミスマッチを減らせます。
私は最初、「リモート可」の求人にも幅広く応募していましたが、面接で条件を聞いて落胆することが多かったです。そこで、「完全リモート」「フルリモート」と明記されている求人のみに絞ったところ、選考プロセスも効率化され、入社後のミスマッチもなくなりました。
スタートアップを狙う スタートアップ、特にシード〜シリーズA段階の企業は、オフィスコストを抑えるために完全リモート体制を採用していることが多いです。大手企業よりも柔軟な働き方ができる反面、安定性は低いため、自分のキャリアステージに合わせて判断する必要があります。
地方企業の東京採用 地方に本社がある企業が、東京のエンジニアをリモート採用するケースも増えています。こうした企業は、優秀な人材を確保するために完全リモートを前提としているため、リモート環境が整っている可能性が高いです。
戦略3: ポートフォリオでリモート適性をアピール
職務経歴書やポートフォリオでは、技術力だけでなく、リモートワークへの適性もアピールします。
リモート環境での成果を数値化 「リモートワーク環境下で、3ヶ月でWebアプリケーションの機能を10個実装」「完全リモートでチーム5人のプロジェクトをリード」など、具体的な数値とともに実績を記載します。
使用ツールを明記 Slack、Zoom、GitHub、Notion、Jiraなど、リモート環境で使用したツールを職務経歴書に記載します。これにより、リモートワークに必要なツールを使いこなせることをアピールできます。
コミュニケーションスタイルを説明 「非同期コミュニケーションを重視し、ドキュメント化を徹底」「週次で進捗レポートを作成し、チームと共有」といった、リモート環境でのコミュニケーション方法を具体的に書きます。
私の職務経歴書には、「リモートワークスキル」という独立したセクションを設け、自己管理能力、コミュニケーション能力、使用ツールをまとめました。これが面接で話題になり、「リモートで働く準備ができている」と評価されました。
戦略4: 給与交渉で通勤手当を考慮
リモートワーク前提の場合、通勤手当が支給されないことが一般的です。年収交渉の際には、この点を考慮します。
月2万円の通勤手当がなくなる場合、年間で24万円の減収になります。これを年収交渉に組み込み、「通勤手当がない分を考慮して、提示額から20万円アップをお願いできますか」と交渉することも可能です。
私の場合、前職では通勤手当が月1.5万円ありましたが、完全リモートの現職ではゼロです。ただし、在宅勤務手当として月1万円が支給されるため、実質的な差は小さくなりました。
在宅勤務手当の確認 在宅勤務手当、通信費補助、光熱費補助などの福利厚生があるかを確認します。企業によっては、月1〜3万円程度の在宅勤務手当が支給されます。
交通費の実費精算制度 完全リモートでも、年に数回の出社や、社外イベントへの参加が必要な場合があります。そうした際の交通費が実費精算されるかを確認しておきましょう。
戦略5: カジュアル面談を積極的に活用
リモート求人の場合、いきなり本選考に進むよりも、カジュアル面談を活用することをおすすめします。
カジュアル面談のメリット カジュアル面談では、選考とは関係なく、企業の文化や働き方について率直に聞けます。「実際のところ、リモートワークはどれくらいの頻度で利用されていますか?」「リモートワークで困ったことはありますか?」といった、選考では聞きづらい質問もできます。
現役社員との対話 Wantedlyやビズリーチのプラットフォーム機能を使えば、現役社員とカジュアルに話す機会を作れます。人事を通さずに現場の声を聞けるため、よりリアルな情報が得られます。
私は、内定を承諾する前に、その企業のエンジニア3人とカジュアル面談を行いました。全員が「リモートワークで問題なく働けている」と話してくれたことが、入社の決め手になりました。
リモートワーク転職後の注意点
リモートワークの職場に転職した後も、注意すべき点があります。私が実際に経験した課題と対策を共有します。
オンボーディングでの孤独感
リモート環境での入社は、オフィスでの入社に比べて孤独を感じやすいです。私も最初の1ヶ月は、「自分はチームの一員として認識されているだろうか」と不安になりました。
積極的なコミュニケーション 入社直後は、遠慮せずに質問することが重要です。Slackで「こんなこと聞いていいのかな」と躊躇するよりも、どんどん質問した方が、早く馴染めます。私は、毎日の終業時に「今日やったこと」を簡単にSlackで共有することで、チームとのつながりを感じられるようになりました。
1on1の活用 上司との1on1ミーティングを定期的に設定してもらい、業務の進捗だけでなく、不安や疑問点も相談します。リモートでは偶発的な会話が生まれにくいため、意図的にコミュニケーションの機会を作ることが大切です。
タイムマネジメントの難しさ
リモートワークでは、仕事とプライベートの境界が曖昧になりがちです。私も最初は、夜遅くまで仕事をしてしまい、燃え尽き症候群になりかけました。
勤務時間の明確化 始業時と終業時をSlackのステータスで明示し、時間外は通知をオフにします。私は、終業時には必ずPCをシャットダウンし、物理的に仕事から離れるようにしています。
ルーティンの確立 毎朝のコーヒータイム、ランチ後の散歩、終業後の筋トレなど、リズムを作ることで、オンオフの切り替えがしやすくなります。
キャリア形成の不安
リモートワークでは、上司や同僚との接点が少ないため、「評価されているだろうか」「キャリアは大丈夫だろうか」という不安を感じることがあります。
成果の可視化 リモートでは、プロセスが見えにくいため、成果を明確に示すことが重要です。私は、月次で「達成したこと」「学んだこと」「次月の目標」をドキュメントにまとめ、上司と共有しています。
スキルアップの継続 リモートだと、先輩エンジニアの仕事ぶりを見て学ぶ機会が減ります。そのため、オンライン勉強会への参加、技術書の読書、個人開発など、意識的にスキルアップの機会を作ることが必要です。
コミュニケーションコストの増加
リモートでは、ちょっとした確認事項でも、Slackで文章を書いたり、Zoomを立ち上げたりする必要があり、コミュニケーションコストが高くなります。
非同期コミュニケーションの活用 すぐに返信が必要ない内容は、Slackのスレッドやドキュメントで共有し、相手のタイミングで確認してもらいます。私のチームでは、「緊急度が低い場合は、返信は24時間以内でOK」というルールを設けています。
定例会議の工夫 毎日の朝会を15分以内に収める、週次の振り返りでチームの状況を共有するなど、定例会議を効率化します。会議のアジェンダは事前に共有し、議事録も必ず残すようにしています。
【実例】私がリモート転職に成功した理由
最後に、私自身がどのようにリモートワーク可の企業に転職したのか、具体的なプロセスを紹介します。
転職前の状況と課題
前職は、東京都内の中規模SIer企業で、週5日出社が基本でした。コロナ禍で一時的にリモートが認められましたが、2023年には完全に出社体制に戻っていました。
私には地方に住む高齢の両親がおり、定期的に帰省する必要がありました。しかし、週5日出社では、長期休暇以外の帰省が難しく、「リモートワークができれば、実家で働きながら親の様子も見られるのに」と考えるようになりました。
また、往復2時間の通勤時間がもったいなく感じ、その時間をスキルアップに使いたいという思いもありました。
転職活動の進め方
ステップ1: 情報収集と準備(1ヶ月目) まず、完全リモート可の企業がどれくらいあるのか、リモートワークを実現するにはどんなスキルが必要なのかを調べました。GitHubでのOSS活動を開始し、個人開発プロジェクトも始めました。
ステップ2: エージェント登録とカジュアル面談(2ヶ月目) ワークポート、レバテックキャリア、マイナビIT AGENTの3社に登録し、「完全リモート希望」と明確に伝えました。同時に、Wantedlyで気になる企業とカジュアル面談を行い、リモートワークの実態を探りました。
ステップ3: 本選考とオファー獲得(3〜4ヶ月目) 5社に応募し、3社から内定を得ました。そのうち1社は「リモート可」と書かれていましたが、面接で「月2回は出社」と言われたため辞退しました。
ステップ4: 最終決定(5ヶ月目) 残る2社のうち、年収が高い方ではなく、リモート文化が根付いている方を選びました。決め手は、カジュアル面談で話した現役社員全員が「リモートで働きやすい」と話していたことです。
成功のポイント
振り返ってみると、以下の3点が成功につながったと思います。
1. 条件を妥協しなかった 「リモート可」ではなく「完全リモート」に絞り、多少年収が下がっても、働き方を優先しました。結果的に、通勤時間がゼロになり、スキルアップの時間も確保でき、長期的には正しい選択だったと感じています。
2. リモート適性を実績で示した 職務経歴書に、GitHubのコントリビューション、個人開発、副業での成果を記載し、「リモート環境でも成果を出せる」ことを証明しました。面接では、自己管理能力やコミュニケーションスタイルについても具体的に説明しました。
3. 企業文化を重視した 給与や福利厚生だけでなく、「本当にリモートワークが機能しているか」を最優先で確認しました。カジュアル面談を通じて、企業の本音を引き出す努力をしました。
転職後の変化
完全リモートになってから、以下のような変化がありました。
時間の使い方が変わった 通勤時間がゼロになり、その分を読書、オンライン学習、個人開発に充てています。技術力が向上し、半年後には社内で新しいプロジェクトのリーダーを任されました。
家族との時間が増えた 実家への帰省も、長期休暇を取らずにできるようになりました。週末を含めて1週間実家で働くこともでき、両親も安心しています。
ストレスが減った 満員電車のストレスから解放され、自分のペースで働けるようになりました。睡眠時間も増え、健康状態も改善しました。
キャリアの可能性が広がった 地方移住も視野に入れられるようになり、将来的には海外でのリモートワークも選択肢になりました。居住地に縛られないキャリアを築けることが、大きな自信になっています。
よくある質問と回答
リモートワーク転職に関して、よく聞かれる質問に答えます。
Q1: 未経験でもリモートワーク可の企業に転職できますか? 未経験からのリモート転職は、正直なところ難易度が高いです。多くの企業は、リモート環境でも自走できる経験者を求めています。ただし、完全に不可能というわけではありません。
未経験からリモート転職を目指す場合は、まずハイブリッド型の企業で経験を積み、その後に完全リモートの企業に転職するというステップを踏むことをおすすめします。また、プログラミングスクールの中には、リモート企業とのパイプがある場合もあるため、そうしたスクールを選ぶのも一つの方法です。
Q2: リモートワークだと年収は下がりますか? 必ずしも下がるわけではありません。むしろ、フルリモート前提の企業は、全国(または全世界)から優秀な人材を集めるため、年収が高い傾向もあります。
私の場合、前職よりも年収が50万円アップしました。ただし、通勤手当がなくなったこと、オフィスランチの補助がなくなったことを考慮すると、実質的には30万円程度のアップでした。
リモートワークで年収が下がるケースは、「地方企業が地方の給与水準でリモート採用する場合」です。東京の企業が地方在住者をリモート採用する場合は、東京水準の給与が支払われることが多いです。
Q3: リモートワークのデメリットはありますか? リモートワークには多くのメリットがありますが、デメリットもあります。
最大のデメリットは、孤独感です。同僚との雑談や、ランチを一緒に食べるといった日常的なコミュニケーションがなくなります。私は、オンラインコミュニティに参加したり、コワーキングスペースを利用したりすることで、この問題に対処しています。
また、自己管理の難しさもあります。誰も見ていないため、サボろうと思えばサボれてしまいます。逆に、仕事とプライベートの区別がつかず、働きすぎてしまうこともあります。
さらに、キャリア形成の不透明さも課題です。上司との接点が減るため、評価やキャリアパスについて不安を感じることがあります。定期的な1on1や、成果の可視化で対応する必要があります。
Q4: 完全リモートとハイブリッド型、どちらがおすすめですか? これは個人の価値観やライフスタイルによります。
完全リモートがおすすめな人は、通勤時間をゼロにしたい、地方や海外に住みたい、自己管理が得意、孤独に強い、という方です。
ハイブリッド型がおすすめな人は、対面でのコミュニケーションも大切にしたい、オフィスの設備を使いたい、リモートに慣れていない、という方です。
私は完全リモートを選びましたが、週1〜2回くらいは誰かと対面で話したいと思うこともあります。その場合は、コワーキングスペースに行ったり、オンラインイベントに参加したりしています。
Q5: 地方在住でも東京の企業にリモート転職できますか? 可能です。むしろ、完全リモート前提の企業であれば、居住地は問われません。
私の同僚には、北海道、沖縄、さらには海外に住んでいる人もいます。ただし、時差がある場合は、コアタイムの調整が必要になることもあります。
また、年に数回の出社が求められる企業の場合、交通費が実費精算されるかを確認しておく必要があります。
Q6: リモートワークに必要な設備はどれくらいかかりますか? 企業から支給される場合もありますが、自分で揃える場合の目安を紹介します。
- ノートPC: 企業支給が一般的
- 外部モニター: 2〜5万円(24〜27インチ推奨)
- デスクとチェア: 5〜10万円(長時間作業するなら投資すべき)
- Webカメラとマイク: 1〜3万円(PC内蔵でも可)
- インターネット回線: 月5,000円程度(光回線推奨)
私の場合、モニター2枚、昇降デスク、ゲーミングチェアを購入し、合計で15万円程度かかりました。ただし、企業によっては在宅勤務手当や設備購入補助があるため、確認してみてください。
まとめ:リモートワーク転職を成功させるために
リモートワーク可のエンジニア求人は増えていますが、求人票の「リモート可」の実態は様々です。転職を成功させるには、以下のポイントを押さえることが重要です。
求人探しの段階では
- 「リモート可」ではなく「完全リモート」と明記された求人を優先する
- 複数の転職エージェントやサービスを併用し、リモート希望を明確に伝える
- カジュアル面談を活用し、企業の本音を引き出す
選考プロセスでは
- リモートワークの頻度、承認プロセス、実施率を具体的に確認する
- 面接官や現役社員に、リモート環境の実態を率直に質問する
- 「名ばかりリモート」企業の特徴を理解し、見極める
自己PRでは
- リモート環境での業務実績を作り、職務経歴書に記載する
- 自己管理能力、コミュニケーション能力をアピールする
- 使用ツールやコミュニケーションスタイルを具体的に説明する
入社後は
- 積極的にコミュニケーションを取り、孤独感を解消する
- 仕事とプライベートの境界を明確にし、タイムマネジメントを徹底する
- 成果を可視化し、キャリア形成の不安を軽減する
リモートワークは、通勤時間の削減、柔軟な働き方、ワークライフバランスの向上など、多くのメリットをもたらします。しかし、成功させるには、適切な企業選びと、リモート環境で成果を出すスキルが必要です。
この記事が、あなたのリモートワーク転職の一助となれば幸いです。理想の働き方を実現し、充実したエンジニアライフを送ってください。
あなたに最適な転職エージェントを見つけよう
転職活動を成功させるには、自分に合ったエージェント選びが重要です。
エンジニア転職ドットコムでは、未経験エンジニア向けに厳選した転職エージェントを徹底比較しています。年代別・職種別・地域別におすすめのサービスを紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。
💻 レバテックキャリアで無料相談する
✅ ITエンジニア専門・業界特化型エージェント
✅ 年収アップ率77%(公式実績)
✅ 技術理解のあるアドバイザーが徹底サポート
※登録後、キャリアアドバイザーより面談日程のご連絡があります
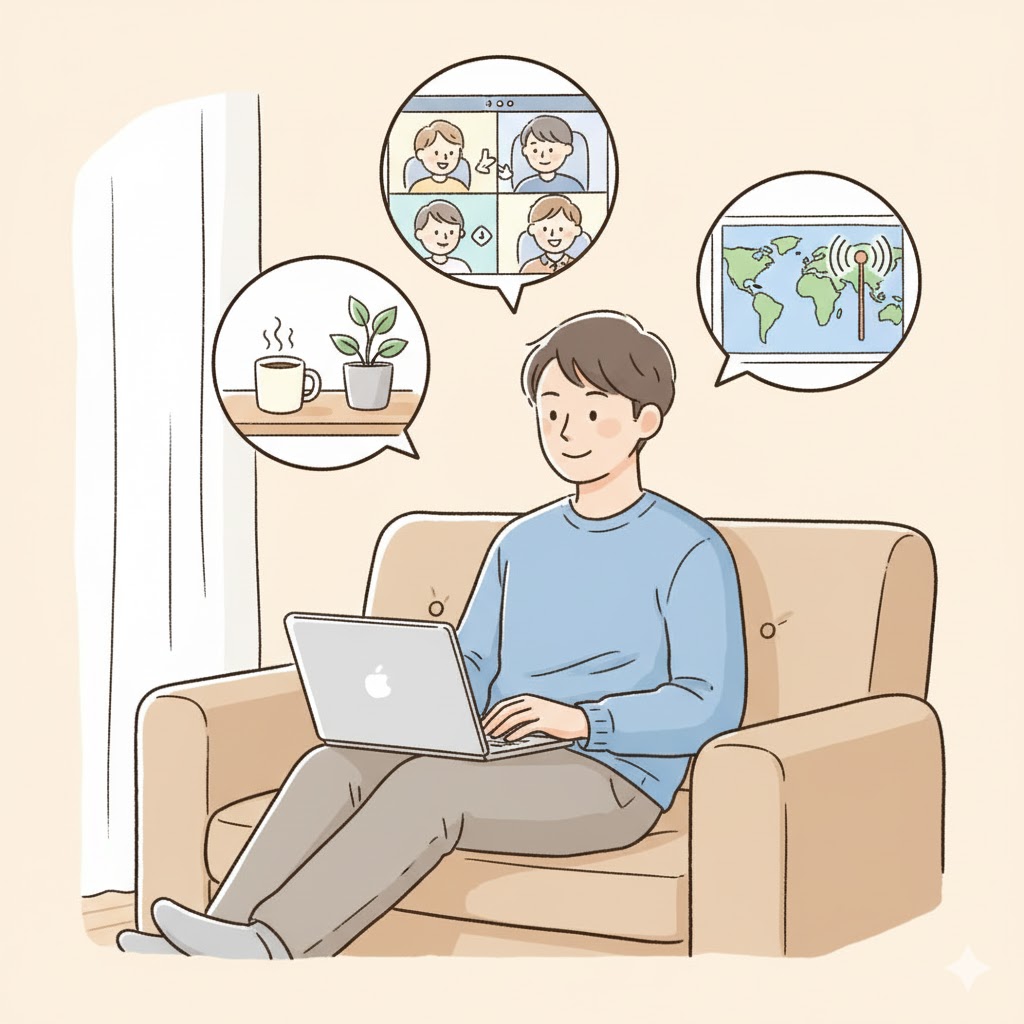


コメント